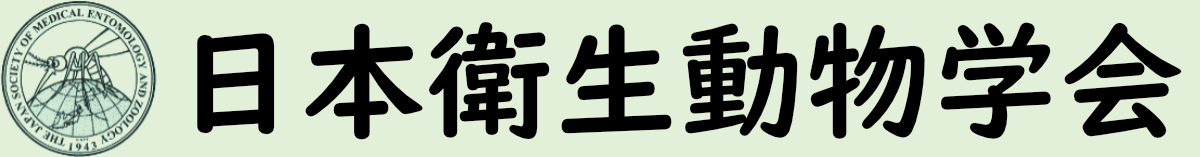「佐々賞」の創設にあたって — 佐々学
去る三月二十八日付の北日本新聞に、日本衛生動物学会で「佐々賞」が創設され、若手の研究者の中ですぐれた業績をあげた者に贈られることとなったと、大きく報道され、私もこの学会と、賞の由来についていろんな方面からご質問や、説明を求められている。
私が去る一九八八年三月に富山医科薬科大学を退官するにあたって、当時の増田克忠副学長が委員長となり、上村清博士が幹事をつとめられて、私の退官記念行事を企画し、多くの方々が募金に応じてくださった。その中から出版費などを除いたあとをこの学会に寄付していただき、これを基金としてその果実をもってすぐれた業績をあげた若手研究者を表彰しようというのが、この賞の趣旨なのである。一九九〇年三月三十日に北九州市の産業医科大学で開催された第四二回日本衛生動物学会総会の席上でその第一回の授賞式が行われ、私も国際大学開学直前の多忙な日程をやりくりしてこれに参列することができた。今回は「渓流に発生するブユ二種の産卵場所と幼虫期の齢数」という研究を行われた大分医科大学の馬場稔氏と、「蚊の体長および吸血量とマラリア原虫のオーシスト形成数との関係」の論文を発表された一盛和世氏との二人にこの賞が贈られることになった。
ところで、こういう基礎研究というものは、一般の方々にとってはその表題を見ただけでは一体何の価値があるのか、どうしてこんな賞が贈られるのか、全然ご理解いただけないのは当然のことで、同じような専門領域の研究者たちにとってさえその内容が理解できなかったり、評価がまちまちであることもあって、それだけに基礎研究に従事している人々も、それをとりまく社会の中で絶えず淋しい思いに耐えてゆかねばならないものであった。その際に、同じ学会の先輩たちが多くの若手研究者の作った論文を熟読してこれに評価を与え、すぐれていると判断したものに対して表彰を行うことは何にも増して励ましとなる。そして今回は表彰に外れた若手研究者たちも、将来はこうした評価を受けようと、その研究や論文作成に一層の努力を注ぐことになる。そういう広い範囲への波及効果も意義が大きいともいえよう。私の退官記念会の募金に応じてくださった方々のご厚志がそういう形で生かされたことを喜んでいただきたい。
この日本衛生動物学会というのは、いろいろな伝染病を媒介して我々を苦しめた蚊、ハエ、ノミ、シラミ、ダニなどの研究を戦時中に始めた数名の仲間たちが、戦後間もなくそうした専門家たちの学会を創ろうではないかと相はからい、当初は数十名の会員で発足したものだが、一九四八年に東京で第一回の総会を開いてからはや四十二年もたったことになる。会員もすでに千名を超えるようになった。ところで、当時の日本ではこういう衛生害虫どもを研究している学者はきわめて少なかった。理学部や農学部で動物学を修めた人たちも、農業害虫の研究はされても、人間の病気を媒介する虫どもの世界には入ってこなかったし、医学部の出身者のごく一部は生理学や生化学のような基礎医学、ないし衛生学や細菌学のような予防医学には進んでも、病気を媒介する虫の研究などやろうとする者はおらず、また全国の医学部をみてもそんな教育や研究をする講座はまったくなかったのである。
そういう私も医学部を出てから伝染病研究所の細菌学教室に入れていただき、結核やハンセン病、腸チフスなどの病原菌の研究をやりたいと志していた。それが戦時中の大部分を海軍の軍医として南の国々を訪れているうちに、マラリア、デング熱、フィラリア病など、蚊が伝染する病気が最も恐ろしいこと、そしてそれを防ぐにはまず蚊の分類や生態の勉強が必要だということを覚えて、思いがけずもこういう専門分野の学問に踏み込んでしまったのである。戦後、もとの研究室に返していただいたが、当時の長谷川秀治部長の寛大なおはからいで、細菌学研究部の中で蚊やダニの研究をつづけさせてくださったのである。
それまで日本にはマラリア、フィラリア病、日本脳炎、デング熱など、いろんな異なった種類の蚊が媒介する伝染病がほぼ全国的にはびこっていることはわかっていたが、蚊の研究は同じ伝染病研究所におられた故山田信一郎先生が生前に手掛けられただけで、日本から二〇種類あまりの蚊を記録し昆虫図鑑などに書いておられた。私は浅沼靖さんや高橋弘さんなどのご協力を得て一九四六年から五年あまり、北海道の北端から九州にかけてリュックサックを背負って満員列車の旅を繰り返し、日本全国から六〇種あまりの蚊を採集して記載し、かつその発生源の特徴や、幼虫、サナギの形態を記録して逐年この学会に報告をしてきた。
そのうちに私は人家内の食品や挨に繁殖するダニ類や、日本全国の山野に繁殖しているツツガムシ類(これもダニの仲間)の研究も始めて、毎年たくさんの新種や未記録種を発見しつづけ、これも衛生動物学会に報告し記載してもらった。こうしているうちに、全国の大学や、地方衛生研究所、薬品会社、害虫駆除会社などから会員が加わり、蚊、ハエ、ブユ、ヌカカ、アブ、ノミ、シラミ、ゴキブリ、コナダニ、吸血ダニ、ツツガムシ、サソリ、毒ヘビ、ネズミ、などなど、人間や家畜の害虫や益虫を広く含めたいろんな研究がこの学会に寄せられて、それらが害虫のいない衛生的な日本の環境改善にも重要な貢献をするようになった。いまの日本がこんなに衛生的で住みよくなったのには、この学会の研究と学会員の貢献がたいへん大きかったと私は自負している。
私はいま、北九州市の産業医科大学で開催された第四二回日本衛生動物学会に二日間出席して私が自分で行った昨年度の日本産ユスリカ類の膨大な新知見のあらましの報告を行い、かつ第一回の佐々賞の授与式に立ちあう感激をいっぱいにして、富山に帰る車中にあるが、七十年を超えた長い人生の中でもこの前後の数日間ほど幸福感に満ちた日々はなかったように思う。この日本衛生動物学会も、いまから四十年あまり前に私が学会を創ろう、それに必要なお金はなんとかなるだろう、と決断してよかった。今日は一九九〇年三月三十一日であるが、明日の四月一日からは、私は新設の富山国際大学の創立にあたって、学長としての責任を果たさねばならない。この大学もたくさんの方々のご協力、ご尽力を得てようやく明日開学されることになった。これからは、私の健康がつづく限り、その発展と、地域社会および国際社会への貢献、そして有能な卒業生の社会への送りこみに、私なりに一生懸命に努力をいたしたい。
出典:佐々学著『随筆集 学究三昧』pp.284-288.実業之富山社,富山,2003.
初出:『実業之富山』実業之富山社,1990年4月
なお、掲載に関し、実業之富山社より許諾をいただいております。