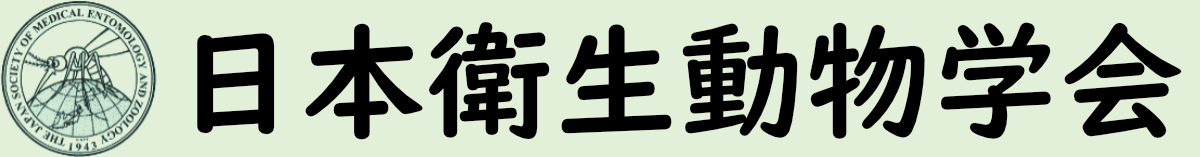平成28年10月12日
|
大会プログラムPDF版 更新情報 |
|
大会プログラム
08:45 受付開始
09:28 開会
09:30~11:35 一般講演①~⑩(農学部1号館8番教室)
<09:30~09:42>
1.なぜネッタイシマカは,日本脳炎ウイルスのベクターにならないのか ―蚊体内での考察―
○佐々木年則,鍬田龍星,星野啓太,伊澤晴彦,澤邉京子,小林睦生 (感染研・昆虫医科学)
<09:42~09:54>
2.人囮法によるヒトスジシマカの生息密度調査における採集時間帯の影響
○木村悟朗,谷川 力 (イカリ消毒(株)・技術研究所)
<09:54~10:06>
3.日本未記録のニセカスミニクバエServaisia亜属の1種
○倉橋 弘1),大宮正也2) (1)感染研・昆虫医科学,2)双翅目談話会)
<10:06~10:18>
4.横浜市街のドブネズミに見いだされた広東住血線虫
○矢部 辰男1),大友 忠男2),原島 利光3),重岡 弘4),山口 健次郎5) (1)ラットコントロールコンサルティング,2)朝日消毒,3)ブラザー興業,4)富士消毒,5)横浜サンセルフ)
<10:18~10:30>
5.能登半島珠洲市における疾病媒介蚊の発生状況調査
○渡辺 護,沢辺京子(感染研・昆虫医科学)
<10:30~10:35>
休憩(時間調整)
<10:35~10:47>
6.食品製造施設で発生したミツモンホソキバガの生態と分布に関する新知見
○富岡康浩1),廣田和樹1),谷川 力1),那須義次2)(1)イカリ消毒(株),2)大阪府立環境農林水産総合研究所農業大学校)
<10:47~10:59>
7.市街地におけるヒトスジシマカとオオクロヤブカのmark-release-recapture実験(2016年)
○津田良夫1) ,前川芳秀1) ,糸川健太郎1) ,木村悟朗2) ,葛西真治1) (1)感染研・昆虫医科学,2)イカリ消毒(株)・技術研究所)
<10:59~11:11>
8.埼玉県内の公園におけるコガタキンイロヤブカの捕集状況について
○佐藤 秀美,長浜 善行,坂田脩 (埼玉県衛生研究所)
<11:11~11:23>
9.神奈川県厚木市で採集されたマダニと吸血源動物との関係解析
○佐藤智美1)2) ,伊澤晴彦2) ,藤田龍介2)3) ,糸川健太郎2)3) ,林 利彦2) ,糸山 享1) ,沢辺京子2)(1)明治大院・農,2)感染研・昆虫医科学,3)日本医療研究開発機構(AMED))
<11:23~11:35>
10.ドライアイスを用いたマダニ類の生息調査
○橋本知幸((一財)日本環境衛生センター)
11:35~12:35 昼食・幹事会(農学部1号館,10番教室)
12:45~13:15 総会(農学部1号館,8番教室)
13:15~13:30 弥生会館へ移動
13:30~15:00 合同シンポジウム(弥生講堂、日本寄生虫学会東日本支部との合同開催)
「節足動物媒介性感染症研究のフロントライン」
座長 松本芳嗣(東大院農・応用免疫学教室)
葛西真治(感染研・昆虫医科学)
S1:
“Cutaneous leishmaniasis: Case management and treatment developments”
Dr. Byron Arana (Drugs for Neglected Diseases initiative, Switzerland)
S2:
“Leishmaniases and their vectors in the Old World and Turkey”
Dr. Yusuf Özbel (Department of Parasitology, Ege University Faculty of Medicine, Turkey)
S3:
“Recent geographic expansion of arboviral diseases: Chikungunya and Zika”
Dr. Anna-Bella Failloux (Department of Virology, Institut Pasteur, France)
15:15~16:03 一般講演⑪~⑭(農学部1号館8番教室)
<15:15~15:27>
11.東京都および日本ペストコントロール協会のハクビシンの相談件数
○谷川 力1)2),玉田昭男1),平尾素一2)(1)東京都ペストコントロール協会,2)日本ペストコントロール協会)
<15:27~15:39>
12.新潟県の日本紅斑熱患者発生地域におけるマダニ保有リケッチア調査
○新井礼子1) ,加藤美和子2) ,青木順子3) ,池田菫4) ,田村務1) ,Marcello Otake Sato5) ,サトウ恵4)(1)新潟県保健環境科学研究所, 2)新潟県はまぐみ小児療育センター,3)新潟県佐渡保健所,4)新潟大学医学部,5)獨協医科大学医学部)
<15:39~15:51>
13.山梨県内におけるヒトスジシマカの分布
〇平林公男,岡田峻典,崔 翔気,田丸直人(信州大学・繊維学部・応用生物)
<15:51~16:03>
14.アキアカネを利用したデング熱媒介蚊の駆除手法の開発
○神宮字 寛,熊谷 祐(宮城大学)
16:10~17:40 特別講演(農学部1号館8番教室)
座長 葛西真治(感染研・昆虫医科学)
特別講演I(T1)
「蚊のゲノム編集研究の最前線」
糸川健太郎(国立感染症研究所昆虫医科学部,AMEDリサーチレジデント)
特別講演II(T2)
「保健所と衛生動物 ‐最近の話題」
矢口 昇(東京都豊島区池袋保健所生活衛生課)
17:40 閉会
17:50 懇親会(弥生講堂フロア)
第68回日本衛生動物学会東日本支部大会のご案内
第68回日本衛生動物学会東日本支部大会を下記の要領にて開催いたします。今回は日本寄生虫学会東日本支部大会と同日開催のため、シンポジウムは共催で行うこととなりました。シンポジウムのテーマは「節足動物媒介性感染症研究のフロントライン」です。また、衛生動物学会側の会場では特別講演も企画しております。皆さまふるってご参加ください。会員以外の方の参加も歓迎いたします。
第68回日本衛生動物学会東日本支部大会
大会長 葛西真治
記
1.開催日
2016年10月22日(土)
2.会場
東京大学農学部弥生キャンパス(東京都文京区弥生1-1-1)
東京メトロ南北線「東大前駅」下車徒歩1分
一般講演および特別講演(農学部1号館8番教室)
共催シンポジウム(弥生講堂)
3.参加費
支部会会員は無料
それ以外の一般参加者は1000円(学生1000円)(当日受付にてお支払いください)
4.参加申し込み
参加の事前申し込みは必要ありません。
5.演題受付
8月15日(月)~9月16日(金)
事務局(east@jsmez.gr.jp)への抄録ファイルの送付をもって受付となります。ファイル送付後48時間以内に返信メールがない場合は、お手数ですが下記事務局までご連絡ください。
抄録ファイルはこちらよりダウンロードしていただけます。
6.懇親会
日本寄生虫学会東日本支部大会参加者と合同で行います。
当日参加、歓迎します。
懇親会参加費は3000円です。当日受付にてお支払いください。
7.昼食
お弁当の予約を承ります。9月16日までにeast@jsmez.gr.jpまでメールでお申し込みください。当日は大学の食堂が営業しておりません。また、周辺の飲食店はご利用いただけますが数に限りがありますので、お弁当を持参いただくか、事務局へのお申込みをお勧めいたします。幕の内弁当とお茶のセットで1000円です。会場内でおとりいただくことができます。お弁当代は大会当日に受付にてお支払いください。
8.演題ファイル締め切り
講演時間は発表10分(1鈴8分,2鈴10分),討論2分の合計12分(3鈴)です。座長は,直前の演者の方に行っていただきます。
口演のファイルはパワーポイントで作成し,電子メール(east@jsmez.gr.jp)に添付で,10月18日(火)までに送信ください。当日はPower Point 2010をご用意いたします。事務局では10MB程度まで受信可能です。大容量の場合や事前送付が難しい場合は事務局までお知らせください。また、動画再生を予定される方も事務局まで事前にご相談ください。
一般口演抄録,口演ファイルをいただいた方で,48時間以内に返信メールがない場合はお手数ですが直接下記事務局までお問い合わせください。
9.支部大会に関する情報発信
今後、大会に関する情報はこのホームページ上で随時お知らせいたしますが、支部会のお知らせメールでも発信予定です。まだお知らせメールへの登録がお済みでない方は、これを機に是非ご登録ください。今回は大会事務局と支部会事務局が同じですので、登録アドレスの変更・修正または削除依頼につきましても同事務局(east@jsmez.gr.jp)が承っております。
10.特別講演
演題1:糸川健太郎(国立感染症研究所昆虫医科学部博士研究員)
「蚊のゲノム編集研究の最前線」
糸川さんは最近の先端的科学技術を駆使して殺虫剤抵抗性機構、特にネッタイイエカ幼虫のピレスロイド抵抗性の主要因であるシトクロムP450解毒酵素の関わりについて精力的に研究を行っている若手研究者です。薬剤抵抗性に関わるP450遺伝子の解析を進めるとともに、この遺伝子をゲノム編集技術を用いてノックアウトし、抵抗性に強く関与していることの直接的証拠を突き止めました。それらの成果は最近Heredity誌やScientific Reports誌に掲載されました。今回は、最近医学の分野でも大きく注目を集めているゲノム編集技術について易しく解説していただき、この技術によって蚊をはじめとした衛生昆虫の研究がどのように進展し、これから発展していくのか学ぶことができたらと思っています。
演題2:矢口昇(豊島区池袋保健所)
「保健所と衛生動物、最近の話題」
矢口昇さんは保健所職員として豊島区の生活環境に関する業務に40年以上携わってこられ、特に衛生害虫やねずみに関する様々な問題に対応されてきました。今回は、トコジラミの被害や防除の現状、最近のヒトジラミ(アタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミ)事情、ねずみ被害、疥癬の集団感染、雨水桝の蚊対策(パンフレットの作成)など最近の話題についてじっくりと伺ってみたいと考えました。これまで徹底して現場主義を貫かれてきた矢口さんだからこそ知りえる、伝えられる最近の衛生動物にまつわる話題をあますところなくご紹介いただけると思います。
11.シンポジウム(日本寄生虫学会東日本支部との共催)
Dr. Anna-Bella Failloux
Department of Virology, Pasteur Institute, Paris, France
Dr. Yusuf Ozbel
Department of Parasitology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir,
Turkey
Dr. Byron Arana
Head of cutaneous leishmaniasis, DNDi, Switzerland